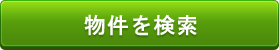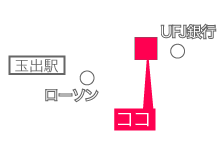住之江区の地域情報

住之江(すみのえ)は、「澄んだ入り江」の意味で、
古代から付近一帯が「住之江」と呼ばれていたことに由来し、『古事記』・『日本書紀』・『万葉集』など古代の文章や和歌ではこの地は墨江・住吉・清江などと記され、いずれも「すみのえ」と読ませています。
大阪市の南西に位置する行政区で、1974年7月22日に住吉区から西部を分離して成立しました。現行の大阪市24区のうちでは最も広い面積を有しており、上町台地の西側に広がり、平坦な地形となっています。古代は地域の大半が海でしたが、大阪湾の沖積活動により砂州が形成され、陸地化が進んでいったと考えらています。
...
全文を表示
古代・中世には現区域の大半は海で、住吉浦・敷津浦などと呼ばれる海原が広がり、南北に海浜が延びていたと考えられている。
室町時代末期には上町台地上にある熊野街道に代わり、紀州街道が主要街道となった。これにより粉浜や安立(安立町)が街道筋として発達することになった。
江戸時代後期には新田開発が進み、おおむね十三間堀川(現在の阪神高速15号堺線)以西に北島新田・加賀屋新田などの新田が形成されていった。
明治時代の町村制施行により、現住之江区の区域には住吉郡墨江村・敷津村・安立町・住吉村と西成郡粉浜村が成立した。
江戸時代後期の新田開発前、この地付近の海が敷津浦と呼ばれていたことから、敷津村の村名となった。
安立町は、安立町と七道領村が合併して成立した。
...
全文を表示
住之江区の地域情報